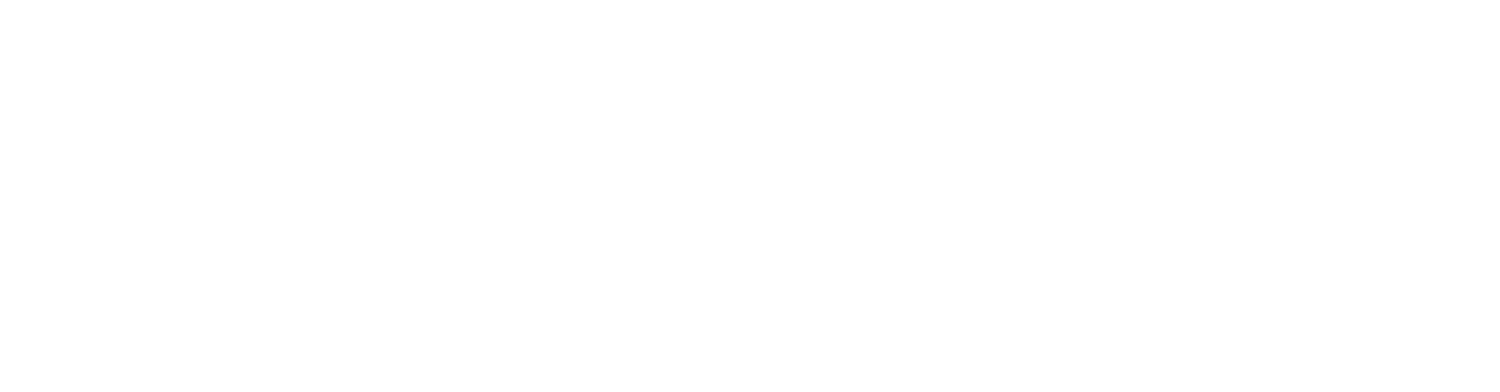はじめに
岩立康男さん著「直観脳」を読ませていただきました。
「直観」は論理思考と逆の言葉に感じますが、実際は密接にかかわっており、相互補完しているものです。直観の働きを理解し、直観をうまく拾うことで、いままで解決できなかった問題の解決策をひらめくことができるようになります。
この本は直観に関する脳の働き・効果について詳細に記載されていて、興味深い内容でしたので、評価・感想をまとめたいと思います。
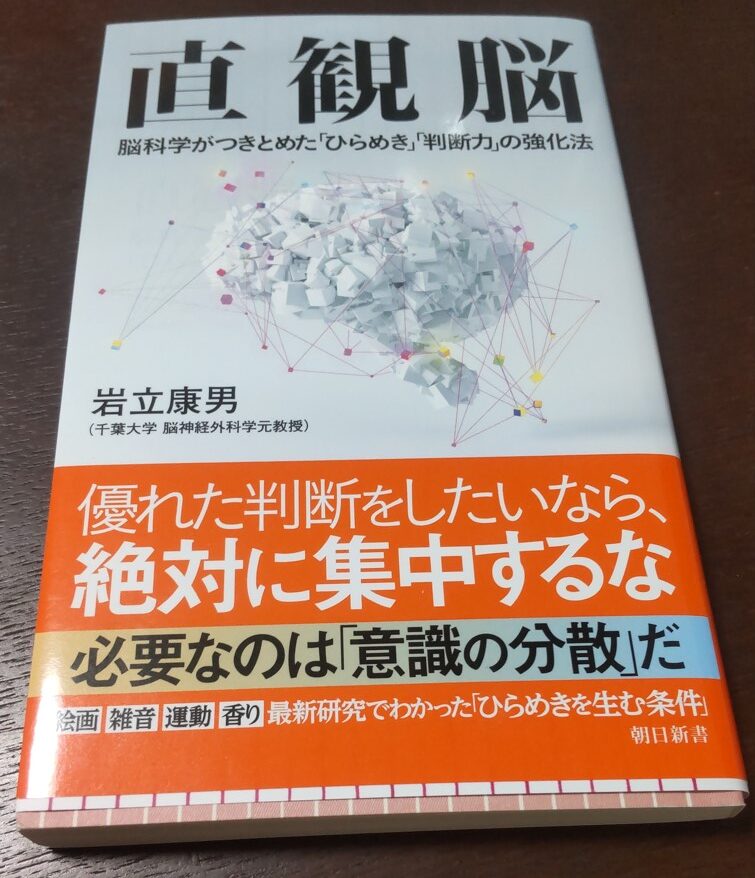
総評
本のあらすじ
「直観脳」は、①直観とは何か、②直観を発動させるにはどうするか、を説明してくれている本です。
直観とは、当てずっぽうの山勘ではなく、過去の経験・知識が蓄積されている脳全体を使った無意識的なアウトプットです。
この直観を如何に多く発動させ、取りこぼさないように、日々どのような意識を持つ必要があるかを具体的に教えてくれています。
直観を発動させるために必要な前提が色々記載されていますが、例えば、集中する際に稼働する脳の部位はごく一部であり直観には逆効果である、などが挙げられています。
本の構成としては、前半部はデータに基づいた直観という事象の説明、後半部は個人としてどう行動すればよいか、という構成です。
評価一覧
| 総合評価 | ★★★★☆ |
| 値段 | ★★★★★ |
| 所要時間 | ★★★★☆ |
| 読みやすさ | ★★★☆☆ |
| 興味深さ | ★★★★★ |
| 内容充実度 | ★★★★☆ |
評価詳細
総合評価
総合評価は★4.5です。
クリエイティブな仕事をしている人はもちろんですが、そうでない人でも、学習や業務上でひらめきは重要ですので、万人におすすめできる本です。
技術的な内容に対して、値段・ページ数も適度ですので、サクッと読めるのも高評価ポイントです。
値段
870円+税。
新書なのでコンパクトかつ安いです。
所要時間
所要時間は3時間。(私は速読はできないので、ゆっくり読んでの時間です)
200ページ程度なので、比較的時間はかからないかなと思います。
読みやすさ
読みやすさは★3です。
細かく章やトピックに分けられているので、そのページで何の話について書いているのか、理解しやすいです。

ただ、脳に関する具体的な専門用語が多いので、記憶の何を司る部位のことか理解が追いつかないこともありました。
興味深さ
興味深さは★5です。
直観とは、という知識的な部分も興味深いですが、私が一番印象に残っているのは、直観がなぜ必要で直観を発動させるためにはどうしていくか、という「個人の考え方」についてです。
私は理系学部出身で、職業もエンジニアですので、常に「論理的に」、「簡潔に」、「根拠を明確に」ということを言われ続けてきました。
ですが、この「直観脳」では、論理的思考だけでは適切な判断はできない、ということが主張されています。
読んだ私としても、確かに論理的思考だけでは不足している、と思う内容になっていて、理系の人やエンジニアにはむしろ直観が重要なのではないかと思います。
最近は「タイパ」という言葉が流行るなど、時間を効率よく使い、より多くの仕事を捌くことが大切とされているように感じます。
ただ、効率を求めて、即座に自分の知っている「型」にはめてしまうことは、物事の本質的な理解を妨げ、直観を発動させるのに不利だと、この本には記載されています。

私としても、時間が掛かるため非効率として避けている事(本質的な疑問をじっくり追及するなど)にしっかり向き合う必要があると感じました。
内容充実度
内容の充実度は★4です。
著者の岩立さんは脳の専門医ですので、脳に関する知識が深く、実験結果についてなどデータに基づいた内容になっています。
また、思考する際の脳の働きを詳しく解説してくれるだけでなく、どうすればより直観を発動させることができるか、という日々の実践内容まで記載してくれています。
科学的な本を読んだけど結局どう日々の生活に取り入れていいか分からない、というのはよくあることですが、この本ではその日から実施できる具体的な内容が書いてあるので、その心配はありません。
おわりに
直観の原理・実践内容ついて知ることができる良い本でした。私は論理的思考が最も重要と思っていましたが、これからの時代ではそれだけでは不十分だと知ることができました。

明日から早速、直観を導くための思考法を実践していこうと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。